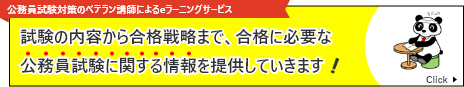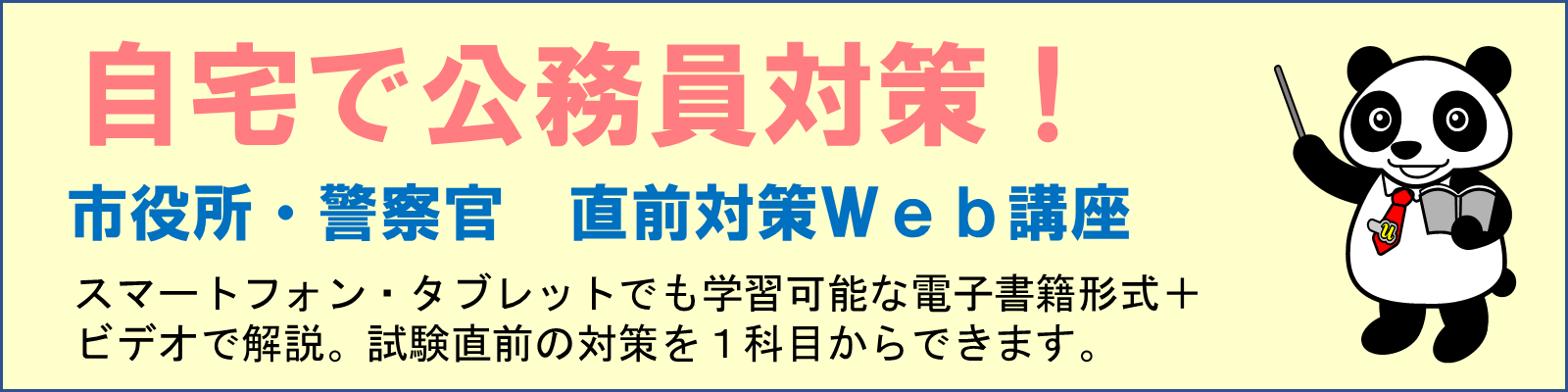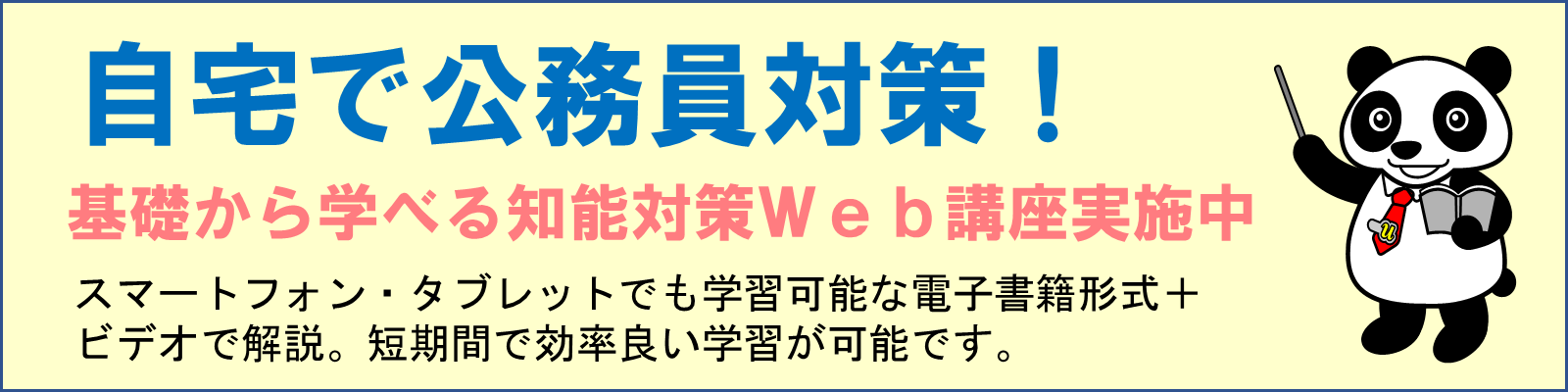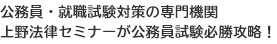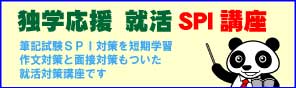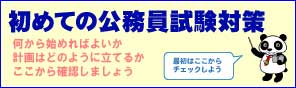公務員に限りませんが、これから就職して長く勤務する職場について関心を持つのは必然です。あらかじめ持っているイメージだけで内定した職場で、いざ働き出したら予想外な職場だった、ということも場合によってはあり得ます。
いわゆる就職ミスマッチが発生するのは、職場環境がどうなっているのか事前の調査不足が一因と考えられます。
では、どうしたら職場環境を調べることができるのか、ここでは以下にその方法について述べていきます。
1.説明会に参加してみる
就職活動における情報収集の基本は、やはり説明会です。説明会は採用側が「ウチの職場はこんな感じです」といった情報を提供してくれるので、参考になります。また、職員の姿を直接目にすることで、職員の特徴などの情報を得ることもできるでしょう。やはり直接的に職員に接することで、初めてわかる感触のようなものは必ずあります。私の知っている受験生も、最終的に応募先を決めたのは、説明会における職員への相談会がきっかけという人もいます。ですので、説明会への参加は職場環境や職員のカラーを知る意味でも、とても有効な手段の一つといえます。また、可能ならインターンシップに応募してみるのも効果的です。インターンシップは、実際に短期間とはいえ職場を直接体験できる貴重な機会です。働いている現場を直接体験することで、職場の空気感や業務内容なども肌感覚で知ることができるのは、他では得がたい経験だといえるでしょう。人数や時期などの制約はありますが、可能なら是非インターンシップに応募してみるのも良いでしょう。
2.現地に足を運んでみる
受験する機関についてはできるだけ事前に現地に足を運ぶことをお薦めします。特に地方自治体を受験する際には、試験日以外でも現地に足を運び、それぞれの自治体の特徴や公的施設などを実際に見ておくことをお薦めします(可能ならメモや写真など記録をしておきたいところです)。HPなどで単に情報を確認するだけでなく、実際に現地に足を運ぶことで、初めて気づくことも少なくありません。また、近年の面接試験では「試験日以外でウチの市に来たことはありますか」という質問をしてくる場合もあります。この場合、こういった質問をすることで受験生の本気度を見ているわけです。その意味でも実際に現地に足を運ぶことはしておきたいところです。
3.「人事行政の運営状況」を調べてみる
そして、「人事行政の運営状況」を確認してみるのも良いでしょう。地方自治体では、各自治体で年度ごとに職員の人事行政の運営状況について、調査・報告が行われています(国家公務員の場合は人事院の年次報告で確認できます)。報告書については、各自治体のHPで公開されているので、そちらで参照できます。報告書では人事行政の運営全般についてデータが記載されていますが、注目したいのは「採用及び退職の状況」です。公務員が退職する場合、大別すると「定年」「定年前早期退職」「普通」「その他」になります。このうち、受験する場合、注目したいのは「普通」退職です。これは定年前に自己都合等により退職する場合が該当します。つまり、民間企業における中途退職に相当します。したがって、「普通」退職が多い場合は、何らかの理由で中途退職している人数が多いことを意味しています。逆に言えば、この人数が少ない場合には、中途退職の人数が少ないと考えて良いでしょう。
仮に「普通」退職が多い自治体を受験する場合には、何故多いのか、何かしらの理由が無いか改めて調べてみると良いでしょう。
>> 〔公務員Web講座のご案内〕 →こちらから
独学の方のための「Web講座」を実施しています。1科目から選択可能です。
効率良い学習で、合格を勝ち取りましょう。