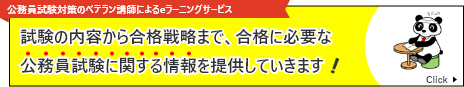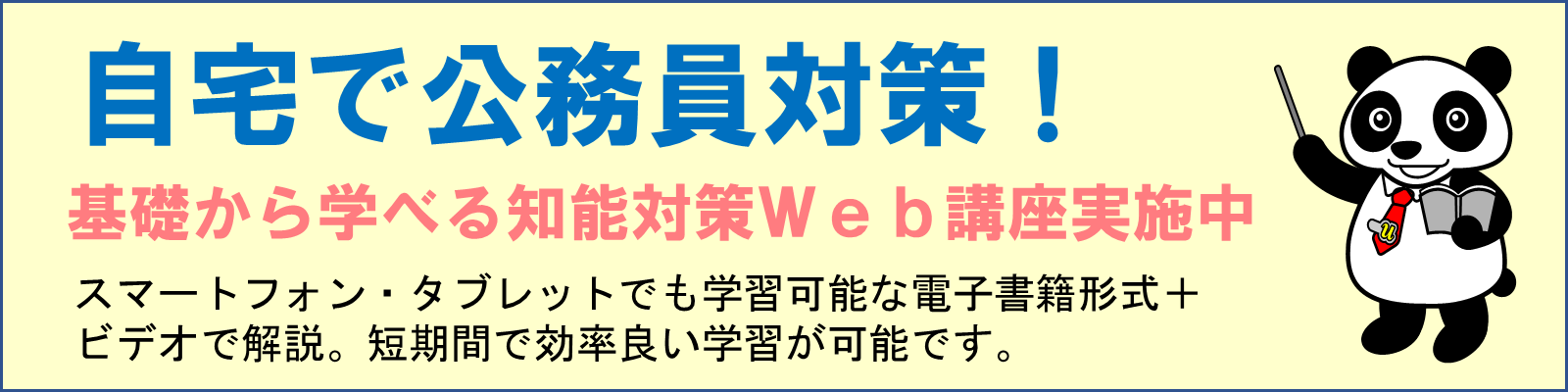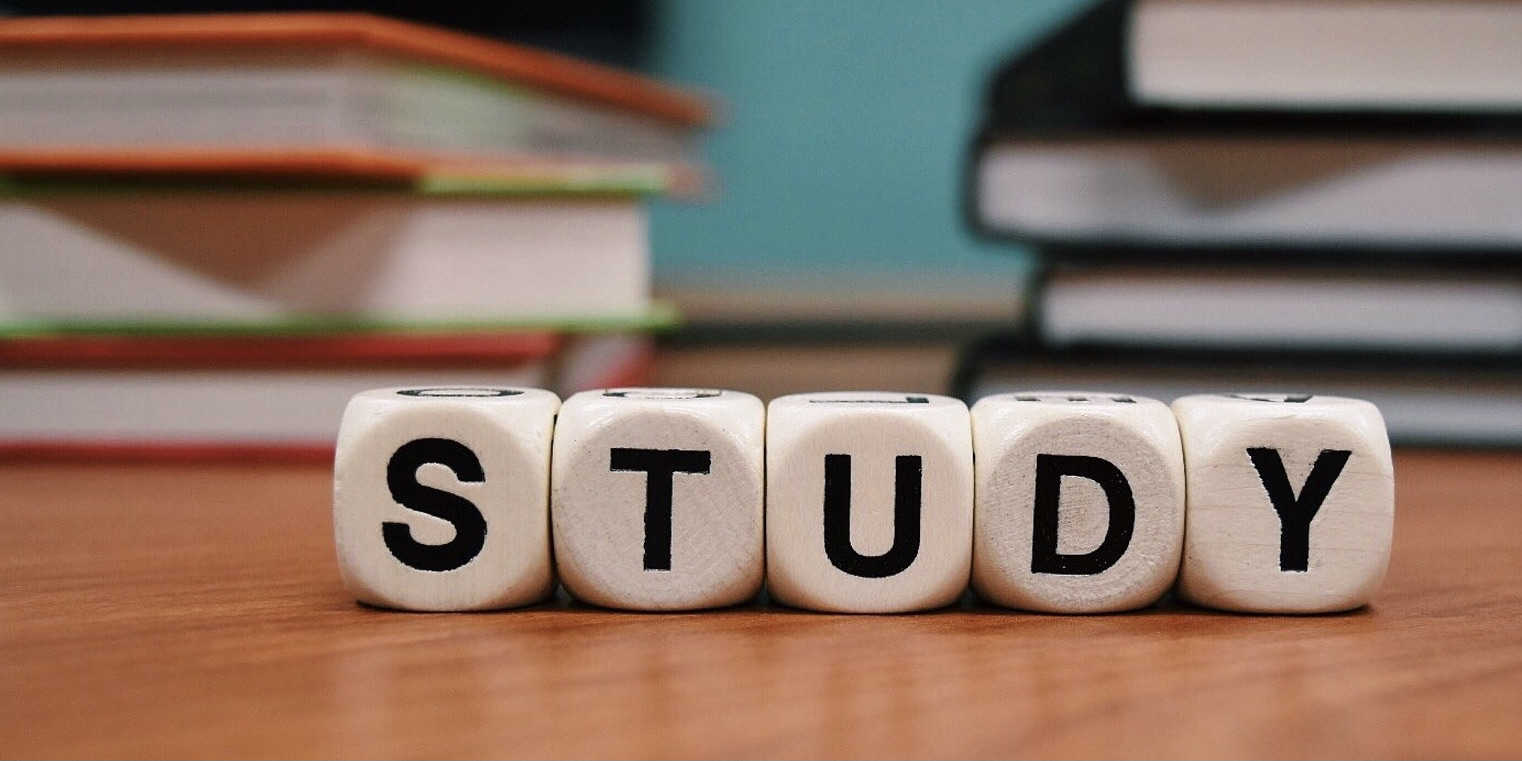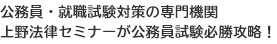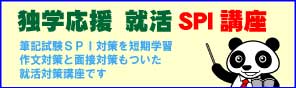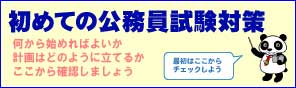問題集の使い方(教養:一般知能)
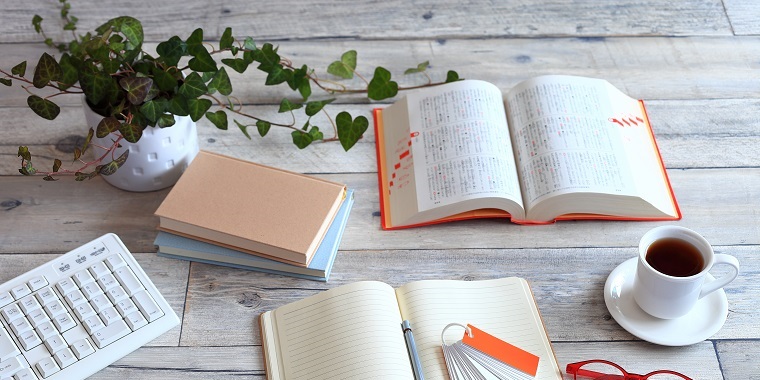
公務員教養試験の合否を左右する大事な科目が一般知能分野です。一般知能分野の科目は、数的推理、判断推理、文章理解、資料解釈、空間把握(判断推理に含まれている場合があります)の5科目です。
思考力、判断力を試す問題で、計算力や国語力も必要とされます。特に数的推理と判断推理が出題数も多く解法がわからないと制限時間内で解くことができません。ここでは、得意になるための学習法をお知らせします。
1.目標に合わせて選ぼう

一般知能の分野は試験によってレベル差があります。どのレベルまで学習しなければならないかを確認して行きましょう。たとえば、市役所の第一志望として、都道府県も受験しようと考えている場合、国家一般職の問題まで手を伸ばす必要はありません。国家公員の法が難易度は高くなりますので無理に問題集として選ぶ必要は無いわけです。
目標とする試験に合わせて購入する問題集を考えてください。
(目標と使用する問題集レベル)
国家一般職(大卒)…国家公務員、地方上級
都道府県…地方上級、東京都・特別区、市役所
市役所…市役所、警察官
警察官(大卒)…警察官、国家一般職(高卒)
2.いきなり本試験はきつい

国家一般職を目指すからといって、いきなり国家の過去問題を解こうとすると難しくていやになる可能性が高いです。過去問題を解く前に問題のパターンと解法を解説した入門書を購入した方が良いでしょう。入門書は「基礎」「入門」と書かれていることが多いので書店で確認してください。
予備校を選ぶ場合は、使用するテキストを事前に確認しましょう。テキストが過去問を解くことに重点を置いている場合、初学者にとっては理解しにくい場合が多いです。
3.初級レベルから理解しよう

一般知能の問題は地方初級(高卒)から国家(大卒)まで、同じ項目が出題されます。
難易度の差は情報量の差からきます。大卒試験が難しいのは高卒試験に比べて問題に含まれる条件が増えてきます。
例えば判断推理の問題で対応関係を例に取りましょう。
対応関係は登場人物と対応する物の組合せを推理する問題です。
初級では登場する人物が5人で対応する物が5種類というケースが多いです。これが大卒となると、登場する人物が6人~7人になったり、対応する物が複数になり、対応する個数から推理するというように、条件が増え、複雑にしているわけです。
同時に多くのことをチェックできるかを見ているので難易度が上がります。
解き方の手順はおなじですので、いきなり複雑な問題から解くのではなく解く流れを初級レベルの問題から学習し、徐々に難易度の高い問題を演習していく方が効率的です。
一般知能の問題は簡単な問題から解いていくことをおすすめします。
>> 〔公務員Web講座のご案内〕 →こちらから
独学の方のための「Web講座」を実施しています。1科目から選択可能です。
効率良い学習で、合格を勝ち取りましょう。