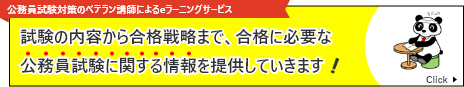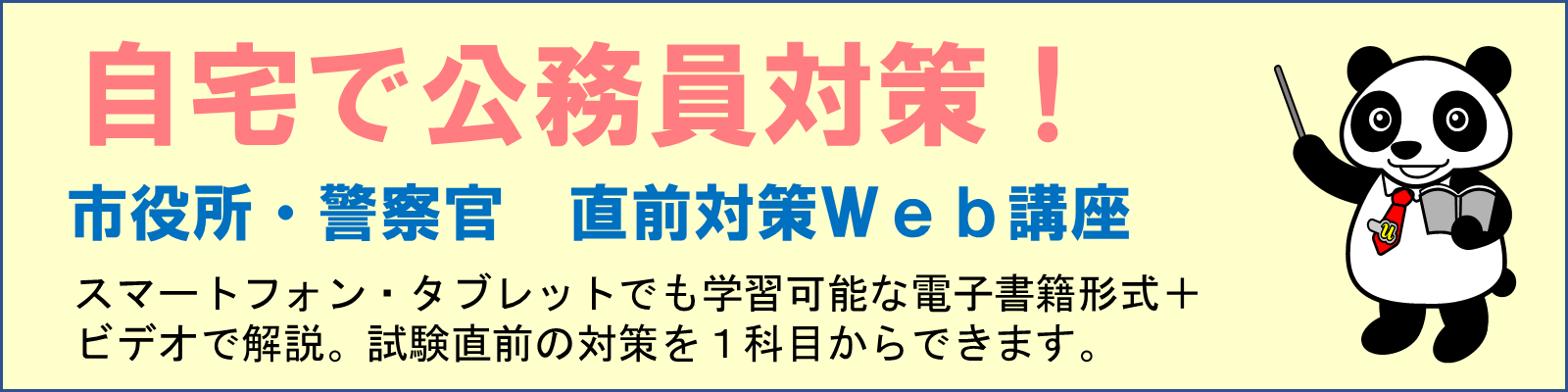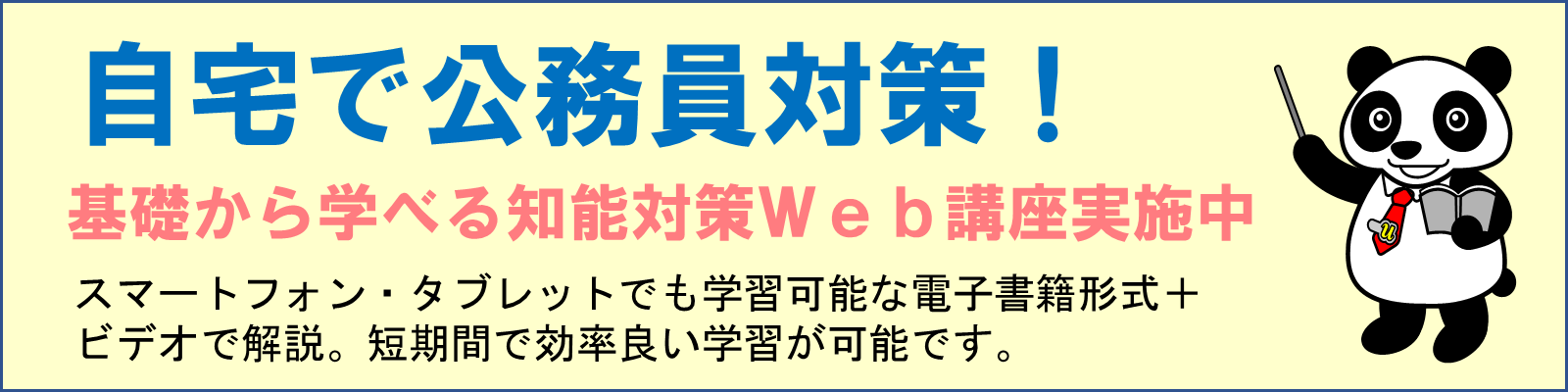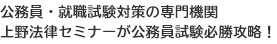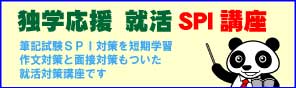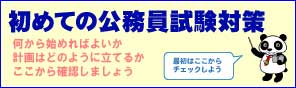法律の王様である憲法は、日本で一番大事な法律です。他のどの法律も憲法に違反してはならないという強い効力を持ちます。今日はそんな憲法の勉強方法のご紹介です。
1.勉強上の戦略と出題問数
憲法は人権分野と統治分野からなります。出題は人権・統治からだいたい半分ずつです。
他の法律に比べて、憲法の条文は103条と圧倒的に少ないです。出題範囲が狭いので論点も少ないです。ということは、点数を稼ぎやすいということを意味します。
論点の多い民法や、遠い分野すぎてわかりにくい行政法が苦手という方は、憲法でなるべく満点を目指すとよいです。
条文を素材とする問題が出ることがあります。そのような問題では、条文の文言を知っている方が得をします。オススメの勉強方法として、暇な時間に憲法の条文の素読をすることです。
教養試験の社会科学にも憲法からの出題があります。専門試験の憲法の勉強をしていれば教養試験の憲法もカバーします。別々の勉強をする必要はないです。
|
|
市役所 |
特別区 |
地方上級 |
国家一般 |
国家総合(法律) |
|
憲法 |
5問 |
5問 |
4問 |
5問 |
7問 |
- 特別区は55問中40題選択
- 国家一般職は16科目中80題中8科目40題選択
- 東京都は記述式
2.人権分野
憲法の前半には人権についての規定があります。
人権分野では、判例を素材とした出題が多いです。勉強をするときは、判例の大まかな内容、論点、結論を整理しておきましょう。ちなみに、憲法の判例にはユニークな名前がついていることがありますが、その名前は出題されませんので覚えなくても問題ないです。
|
テーマ |
出題頻度 |
|
外国人の人権 |
B |
|
新しい人権 |
A |
|
平等権 |
A |
|
思想・良心の自由 |
B |
|
信教の自由 |
A |
|
表現の自由 |
A |
|
職業選択の自由 |
B |
|
財産権 |
A |
|
人身の自由 |
B |
|
選挙権 |
C |
|
社会権 |
A |
- Aがよく出る、Bが出る、Cがたまに出るの順
3.統治分野
憲法の後半は、国のシステムを定めた統治分野です。立法権、行政権、司法権、地方自治に関する規定があります。
こちらは判例が素材になっての出題というよりも、制度に関する出題のほうが多いです。制度がでてきたら、目的・趣旨を整理するようにしましょう。例えば、国会は二院制という制度で運営されています。なぜ院が二つあるのかというと、一つの院が行き過ぎたときに歯止めをかけるため、多様な民意を国会に送り込み多様な法律を作るため、という趣旨があります。
この趣旨を覚えておくと、わからない問題が出たときの考える上でのヒントになります。
|
テーマ |
出題頻度 |
|
国会の活動 |
A |
|
国政調査権 |
B |
|
国会議員 |
B |
|
内閣総理大臣 |
A |
|
議院内閣制 |
B |
|
司法権の限界 |
A |
|
裁判所 |
B |
|
違憲審査権 |
A |
|
地方自治 |
B |
ポイント
① 出題範囲が狭く、勉強しやすい
② 人権分野は判例が素材になることが多い
③ 統治分野は制度趣旨をチェック
>> 〔公務員Web講座のご案内〕 →こちらから
独学の方のための「Web講座」を実施しています。1科目から選択可能です。
効率良い学習で、合格を勝ち取りましょう。専門科目は絞って学習しましょう。