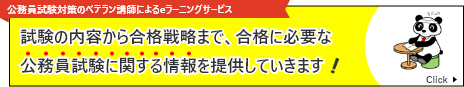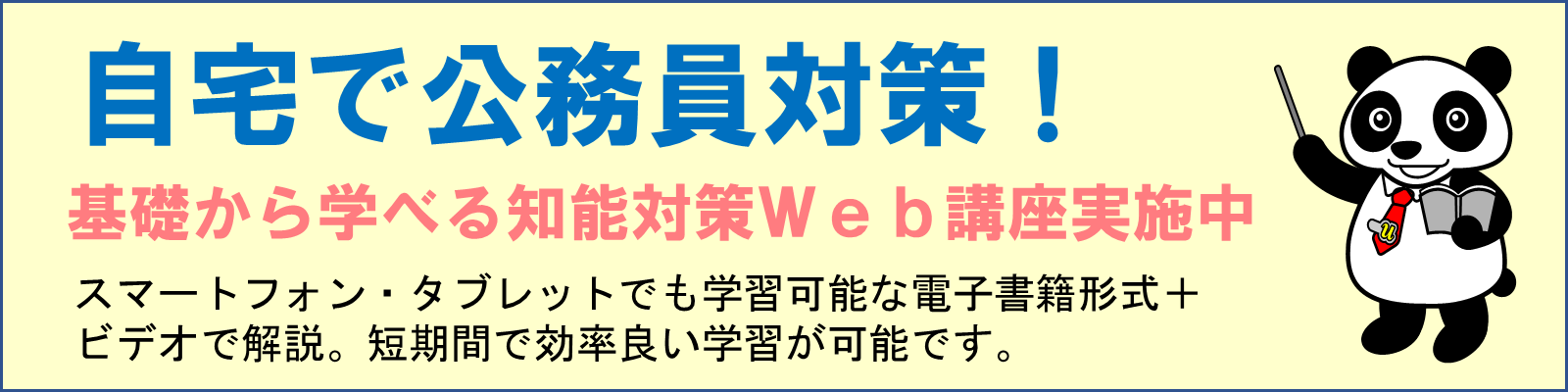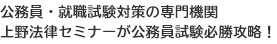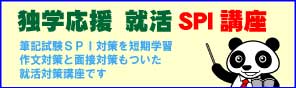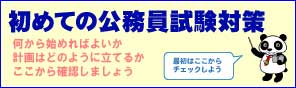人物評価の種類

公務員試験の評価方法は、「学力評価」と「人物評価」の二本立てとなっています。「学力評価」は、「一般教養試験」(高校までに学んだ範囲の筆記試験)と、「専門試験」(大学で学んだ専門分野の筆記試験)によって行われ、「人物評価」は、エントリーシートなどの記述内容、論作文・小論文試験、面接試験などによって行われます。
近年は、「人物評価」を重視する自治体が多くなっています。各自治体の職員採用試験実施状況(申込者数、受験者数、一次試験通過者数、最終合格者数)を見ると、「学力評価」(一般教養試験、専門試験)では比較的大勢を通過させているのに対し、「人物評価」(面接など)で大部分を落とし、合格者を一気に絞り込む傾向がみられます。つまり、合格して採用されるためには、「学力」について一定の基準(概ね、6割以上の正答)を満たした上で、受験者自身の「人間性」が評価される必要があるのです。「人物評価」の対策をしっかり行うことが、合格するために必須の条件となっています。
この記事では、「人物評価」の種類についてご紹介します。
1 エントリーシート、 履歴書
エントリーシート、 履歴書は、出願時に願書と共に提出します。近年は、インターネット上の自治体の職員募集サイトで必要事項を入力し、インターネット上で出願させる自治体が増えている一方で、従来通り、自治体で配布する出願書類一式を入手して、手書きで記入し、郵送などで出願させる場合もあります。
エントリーシート、履歴書には、自分の氏名、住所、連絡先(携帯番号、メールアドレス)、学歴(社会人の場合は職歴も)、賞罰を記入するほか、志望動機、志望職種、保有する資格、特技、得意科目などを、ありのままに記入します。
内容に不備や虚偽があった場合、不合格となる場合もあります。これは、「受験者が決まりを守り、正確な仕事ができるかどうか」について評価されるからです。記入の際は慎重に、間違いがないかどうか、必ず確認しましょう。手書きで記入する場合は、「丁寧に、読みやすい字」で書きましょう。また、小さい字でびっしりと記入すると、内容を読んでもらえません。「読み手に対する思いやりがない」と評価され、不合格となる可能性が高くなります。大きめの字で、字間・行間を空けて、一目で内容が理解できるように書きましょう。
2 論作文・小論文
論作文・小論文試験は、概ね、一般教養試験や専門試験と同じ日に実施されます。筆記試験ではありますが、評価は面接などと共に「人物評価」として行われます。書き方のコツは、次の通りです。
(1)事前に、過去に出題された課題を調べ、同じ制限字数・制限時間で実際に書く。
(2)丁寧な字で、読みやすく書く。
(3)内容を理解しやすい構成で書く。
何回も書く練習をして、時間内に規定の字数で、自分の人間性を評価してもらえるような内容で書けるようになりましょう。
練習で書いた後は専門家に添削してもらい、内容を向上させましょう。
3 面接カード
面接カードは、筆記試験を通過した受験者に配布されるので、必要事項を記入し、面接試験の前に提出します。 様式は自治体によって異なりますが、概ね、次の項目について記入することになります。
(1)志望動機、志望職種、希望する配属先
(2)自分の長所、特技、得意科目、保有する資格
(3)大学時代に、自分が力を入れたこと
(4)公務員として、自分が取り組みたいこと
面接カードの記載内容に誤りや虚偽があった場合、不合格となります。慎重に、間違いが無いように記入しましょう。加えて、「丁寧に、読みやすい字」で書きましょう。
面接カードの書き方のコツは、「面接で聞いて欲しいことを、具体的に、簡潔に書く」ことです。面接官は、面接カードの記入内容を元に、受験者が公務員としてふさわしいか評価するために質問します。自分が聞いて欲しいことを具体的に、簡潔に書くことで、面接官の質問内容が予想できるようになり、どのように答えれば自分の良さを主張できるかについて、事前に検討しておくことができるようになります。
4 個別面接
面接と言えば、個別面接が一般的です。人物評価の中でも、最も重要な試験です。まずは、社会人としてのマナーを身につけておきましょう。
また、自分の人間性を評価してもらえるよう、面接官の質問に対して、明るい表情で、大きな声で、ありのままに、具体的に、簡潔に、ハキハキと答えましょう。
答える時間が長いと、評価が下がります。自己中心的で、他者に対する思いやりがないと評価されてしまうからです。簡潔に、手短に答えましょう。
5 集団面接
一部の自治体や職種で実施されます。
社会人としてのマナーを身につけておきましょう。
また、自分の人間性を評価してもらえるよう、面接官の質問に対して、明るい表情で、大きな声で、ありのままに、具体的に、簡潔に、ハキハキと答えましょう。
集団面接で注意すべきなのは、次の2点です。
(1)他の受験者の行動や発言に流されないようにしましょう。特に、他の受験者がマナーを守っていない場合でも、自分だけは社会人としてのマナーを守りましょう。他の受験者の発言内容はしっかりと聞きましょう。
(2)「答えられる人は手を挙げてください」と言われた場合は、真っ先に手を挙げて答えましょう。一番に手を挙げて答えた受験者だけが、高く評価されるからです。公務員として必要な、「積極性」、「迅速な対応」 が評価されます。反対に、最後まで手を上げず答えない場合、評価が大きく下がります。注意しましょう。
「端から順番に答えてください」と指示された場合は、面接官の指示に従って、順番に答えましょう
6 集団討論
一部の自治体や職種で実施されます。受験者が5~6人程度のグループに分かれ、示された課題についてグループ内で討論を行い、最後に、各グループの結論を発表します。
集団討論では、「結論」よりも、「討論の過程」が大きな評価対象となります。「民主的」で、「公平」で、「全員で協力」して、「制限時間内」に結論をまとめましょう。公務員として必要な「協調性」、「公平性」が評価されます。
集団討論では、グループ全員の評価が「同じ評価」となります。
誰か一人だけが発言し続けたり、何も発言しない人を放置したり、誰かの意見を完全否定したり、誰かの人格を否定したりすると、グループ全体の評価が大きく下がります。注意しましょう。
また、時間は概ね「60分間」であり、比較的短い時間で結論をまとめることが求められます。時間経過には特に注意し、手際よく討論を行って、制限時間内に結論をまとめましょう。
なお、集団討論は、勝ち負けを競う「ディベート」ではありません。グループの皆で協力して、課題に対してのより良い結論を、制限時間内でまとめていきましょう。
人物評価の位置づけ
人物評価の種類
面接試験の流れ
面接評価、コンピテンシー
面接準備
面接カードの書き方
面接カードと質問
面接評価のポイント
個別面接
集団面接の注意点
集団討論の形式と流れ
>> 〔公務員Web講座のご案内〕 →こちらから
独学の方のための「Web講座」を実施しています。1科目から選択可能です。
効率良い学習で、合格を勝ち取りましょう。