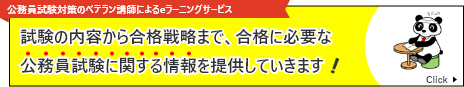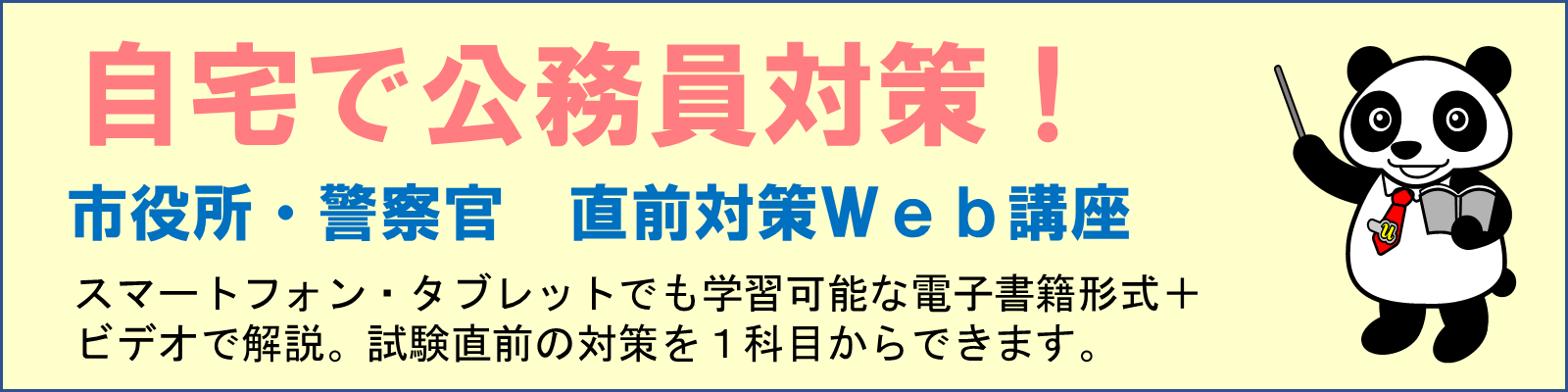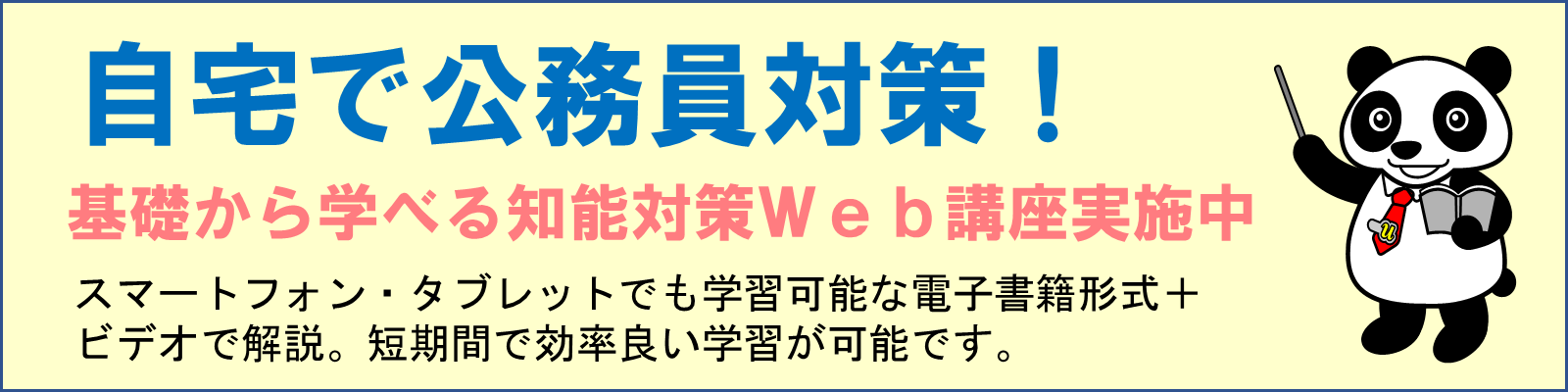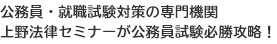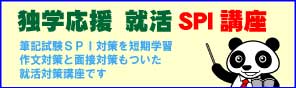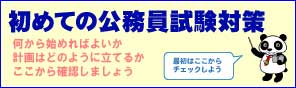事務系の行政職を目指す方が受けることになる専門試験。専門試験と聞くと躊躇しがちですが、意外とそうでもなさそうです。裏話もご紹介します。
1.最近の専門試験事情
専門試験とは、法律学・経済学・行政学に関する試験のことです。事務系の行政職の方であれば、この三科目は、公務員の業務をする上での前提知識となります。公務員になる前にその素地を身に着けてほしいという自治体側の気持ちが見えますね。
教養試験のほかに、専門試験もあるのか…という受験生のため息が聞こえてきそうです。確かに、科目が増えるとハードルは高くなりそうです。
ただ、ここからが公務員試験戦略上興味深いところです。
最近の流れをみると、専門試験を課さない自治体(市役所レベル)が増えてきています。専門試験を回避したい受験生が、専門試験を出題しない自治体へと流れてしまうのを防ぐためです。専門試験をなくし、受験の門戸をできるだけ大きく開き、いろいろな可能性を持った受験生を合格させたいという自治体側の意図の表れです。
でも、専門試験を課さない自治体を選ぶ前に、考える必要があります。多くの受験生は専門試験を避けます。そうすると、専門試験を課さない自治体に受験生が集中し、倍率も上がってしまいます。もちろん教養試験で高得点を狙い、面接でよい印象を残せば、倍率は心配には及びません。ただ、採用人数が極端に少ない自治体の場合は、倍率を全く考えないというのはリスキーです。中には、採用予定人数が数名という自治体もあります。
専門試験の勉強をしておいたほうが、受験できる自治体の数は増えます。また、他の受験生との競合も避けることができます。
専門試験のある自治体を選ぶかどうかは、みなさんの戦略次第なのです。
ちなみに、過去にある市役所を受け一次試験(教養と専門試験)に合格した方から、このようなことを聞いたことがあります。
「私は専門試験の勉強を一分もしなかったんです」。その方は、専門試験に関する学部でもなく、大学での勉強が専門試験に役立ったとも言いにくい状況でした。
すべての自治体にそのようなケースがあてはまるかはわかりませんが、専門試験の足切り点数を内部では設けていないのかもしれませんね。
2.択一式と記述式の違い
専門試験の出題には2パターンあります。択一式(5つの選択肢から答えを選ぶ)と記述式(文章を書いて説明する)です。
圧倒的に多いのは択一式です。全体の8割くらいの自治体は択一式を採用しています。記述式は、例えば東京都Ⅰ類Bや警察事務で採用されています。
きっと受験生は記述式に大きな不安をお持ちだと思います。専門的な内容を文章にするなんて難しすぎる…という気持ちになりますね。
ここも実は盲点があります。択一式では、答えが間違っていれば絶対点数が入らないという容赦のない現実があります。例えば、正解が選択肢2であれば、選択肢3を選んだ時点で点数はもらえません。
この点、記述式ではなにかしらの文章が書いてあれば、内容が絶対的に間違っていなければ部分点を期待できるのです。
気の持ちようですね。択一式と記述式では、問われることは同じです。基本的には勉強する内容が同じということです。記述式を敬遠しないようにしましょう。(記述式に関する情報は該当ページをご覧くださいませ)。
ポイント
① 専門試験を出題する自治体は減少傾向にある
② 専門試験を課しても、足切り点数を設けていない自治体もある
③ 択一式と記述式のメリット・デメリットを意識しよう
>> 〔公務員Web講座のご案内〕 →こちらから
独学の方のための「Web講座」を実施しています。1科目から選択可能です。
効率良い学習で、合格を勝ち取りましょう。専門科目は絞って学習しましょう。